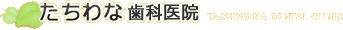6.X線写真の整理・保存,被曝防護と患者への説明
カテゴリー: デンタルX線写真の撮り方・読み方
登録日: 2007/12/05
はじめに
これまで,5回にわたり,デンタルX線写真の撮影,現像,読影について述べ
てきた.
しかし,これらはあくまで,歯科医療の一資料の作成方法と,活用(診断)であ
り,資料としての価値を高めるためには,その管理方法が重要となる.言い換え
ると,これまで述べた撮影法,現像法に管理が加わってはじめて,X線写真のハ
ードウェアが,完成すると考えている.
また,我々術者としては,X線写真撮影の有効性を知るが故に,何のためらいも
なく(?),放射線を患者に照射しているが,患者はどう思っているか考えるこ
とも必要である.患者さんよりX線撮影の理解を得るためには,歯科医側より適
切な説明がなされなければならないが,そのために必要な知識を再度整理した
い.これは,医療従事者側の放射線防御にも役立つと考える.
最終回は,この2点について,筆者の考えを述べてみたい.
X線写真の整理・保存
初診時に,X線診断と患者への説明に使用する以外に,筆者がX線フィルムを
見ながら,歯科治療を行う場面は,髄室開放,根管形成,根管充填,メタルコア
ー装着,除石,ルートプレーニング,窩洞形成,歯冠形成,経過観察等である.
このように,X線写真は,撮影した日以外に読影する事も,かなりある.したが
って,X線写真の管理は,筆者にとっては重要な項目である.幸いなことに,筆
者が勤務した上野歯科医院(北九州歯学研究会,上野道生先生)では,すでにこ
のシステムは構築されており,自院開設の折も,そのまま同じシステムを導入し
た.従って,これから述べる事もほとんど,上野先生に教えていただいた事であ
り,現在も感謝の念にたえない.
X線フィルムの中には,画像として口腔内の様々な情報が入っているが,撮影
のデータは,簡単に入れることができない.鋭利な器具でひっかいたり,器械を
使って,文字をフィルム面に入れたりする方法もあるが,筆者はあまり好きでは
ない.また,全顎14枚法と,それ以外の場合は若干,整理,管理の方法が異な
る.
十分な定着・水洗により,長期保存に耐え得るように処理したX線写真を,後
日読影する必要がある時,短時間に抽出できるようにするために,当院では以下
のシステムをとっている.
・フィルムにはあらかじめ,鉛ナンバーシール(NND,⑭ニックス)を貼ってお
く.図1.
・X線写真撮影時に,ワンタッチ式フィルムマウント(FMO,⑭阪神技術研究
所)に,フィルム番号,日付,撮影部位,撮影目的,撮影者を,記入し,あらか
じめ決められた箱に入れておく.なお,この時,14枚法を取った場合は,その旨
を,フィルムマウントに書いておくと.図2.
・現像,定着,水洗まで終えたフィルムは,一晩乾燥させておく.
・翌朝,診療開始時に,番号をあわせて,フィルムマウントにフィルムを貼る.
14枚法の分は,14枚法用のシート(阪神技研)に入れてゆく.枚数が少ないとき
は,モンレックス(東京歯科産業⑭)を使う.図3.
・組み合わせたX線写真は,バインダー(コクヨ・Gファイル)に綴じた専用の
ビニールシート(ASD,⑭阪神技術研究所)に,番号順(日付順)に整理する.
14枚法のフィルムマウントもそのまま,整理する.図4.
・バインダーの最新版は,X線写真整理をする場所(診療室内)に,それ以前の
バインダーは,診療室内の書架に配置する.図5.
・14枚法用のシートは,検査表,指導記録,その他とともに,カルテファイルに
入れる.図6.
システムの長所・短所
先に述べたとおり,当院では一人の患者のカルテは,その他の資料とともにフ
ァイリングする様にしている.したがって,ある一人の患者の当院でのX線写真
撮影の(治療の)履歴は,その場ですぐわかるようになっている.このことを前
提として,このシステムの長所を述べる.
まず,最大の長所としては,過去のX線写真を探す時間が短い事があげられ
る.14枚法は常に,カルテファイルに挟んであるし,フィルムマウントに貼って
ある分も,過去のカルテにより,撮影の年月日さえわかれば,だいたい20秒程
で,出してくることができる.この,短時間で自分の臨床の予後を振り返ること
ができるのは,非常に良いことであると思う.自分の治療の結果が良いのを確認
できるのは,うれしいものである.
次に,14枚法のシートは,プラスチックフィルムのカバー,フィルムマウント
は,ビニールシートに入っているので,裸フィルムの場合と比べて,キズやほこ
りが付きにくいことがあげられる.筆者のX線フィルムのキズは,ほとんどが,
乾燥前に付いたものか,発表用に,スライドシートに入れてからのものである.
このシステムの短所としては,スライド用のプラスチックマウントに入れ替え
るときに,フィルムマウントに付いているフィルムを固定する接着剤が,フィル
ム面に残る事があげられる.貼ってから時間が短い場合はさほどではないが,古
くなると,接着剤が劣化して,扱いにくくなる.周囲0.5・程であるが,スライ
ドにして見るときには,見苦しい.現在,改善策を模索中である.
患者さんにX線撮影を理解していただくために
読者の皆様の中で,患者にX線撮影の事前説明をした際に,自分が妊婦である
ことを告げられ,X線撮影の胎児への影響を問われた経験のある方は,多いので
はなかろうか.
また,妊婦以外でも,全額14枚法のように,多くの枚数の撮影の際に,その理由
を問われることもあるのではなかろうか.
筆者は,チェルノブイニ原発事故,つくば市のウラン工場事故など,放射線障
害に関する,世間の関心事が続く中,術者と患者相互理解の上で,しっかりとし
た知識に基づいたX線写真撮影を行いたいものであると考えている.そのため
に,教科書的な,すこし堅苦しい,事項を述べるがご勘弁いただきたい.
放射線防護の為の基礎知識
我々が,X線診断に利用する放射線の性質としては,1.物質を透過する性質
(透過作用)2.写真フィルムを感光させる性質(感光作用)3.ある物質にあ
たると蛍光を発生させる性質(蛍光作用)4.物質を透過するさい、その物質を
作っている原子や分子にエネルギーを与えて、原子や分子から電子を分離させる
性質 (電離作用)等がある.
これらのうち,透過作用、感光作用、蛍光作用を利用してエックス線検査が行わ
れ,電離作用により,放射線による身体への障害が起きる.
放射線障害の種類としては,身体的影響(早期障害,晩発障害),胚および胎
児に及ぼす影響,遺伝的影響等が挙げられる.ここでは,患者から問われること
の多い,発癌性の問題と,妊娠への影響について述べたい.
患者は,デンタルX線写真のフィルムの大きさから,経験的に歯科での放射線
被曝量は非常に少ないことを知っている.しかし中には,14枚法の時のように,
照射の回数が多くなると不安に思うのも理解できる.このようなときには,ある
一面,申し訳ない気もするが,筆者は医科の胸部X線撮影を,引き合いに出して
説明を行っている.インターネットで,放射線について検索すると,医科では患
者のX線検査に対する不安を取り除くための,対外的な活動が盛んに行われてい
る.様々な情報が公開されており,これを歯科のX線写真撮影が安心である根拠
として利用させてもらっている.以下はその概要である.
デンタルX線写真の発癌性について
人間の体は放射線を多量に受けると、白血病やガンになる可能性があることは
過去の調査よりわかっている.しかし、その放射線の量は、1,000ミリシーベル
ト以上である.この放射線量以下では人体にガンが発生したという確証はない.
一方,集団検診などで使用されるエックス線検査の放射線量は、胸部エックス線
写真1枚で約0.1ミリシーベルトなので、約1万回検査を受けないと1,000ミリシ
ーベルトの量にはならない.歯科のX線写真撮影に使う放射線の量は,もっと小
さいうえ,鉛の入った防護衣も使用しているので,心配しなくても良い放射線量
である.
デンタルX線写真の妊娠への影響
妊娠の場合は,受精後1~2ケ月以内の,本人に自覚のない時期の事より説明し
ているが,なにぶん微妙な問題でもあるので,状況により,説明の仕方を考慮し
ている.
放射線が胎児に与える影響は、受精後から8日までの着床前期であれば、流産
を起こす可能性があるが,この場合本人が妊娠に気付かない事もある.そうでな
い胎児は正常に発育する.受精後2~8週の器官形成期が奇形発生の可能性の最も
高い時期である.しかし,このような影響を与える最低の放射線量は、50~100
ミリシーベルトを越える線量といわれており,歯科でのX線撮影では,全く問題
ではない.
なぜなら,X線を直接照射する胸部エックス線写真1枚で,約0.1ミリシーベルト
なので、胎児に対しての影響は,胸のエックス線写真であると約1,000回を一度
に受けないと100ミリシーベルトの量にはならない.歯科で検査に使用される放
射線量は非常に少なく、さらに鉛の入った防護衣も使用しているので,このよう
に歯科でのX線検査による影響で奇形等の発生する可能性はほとんどない.
放射線防護の対象者
まず最初に述べたいのは,誰のための被曝防護かということである.
患者のX線写真撮影を行うとき,患者にとっては様々なメリットがある反面,X
線に曝露するという,デメリットもある.当然それに対する影響を最小限にする
ために,防護衣の装着は必要である.図7.他方,現在新規に歯科医院を開設す
る際には,X線撮影室の設置が義務づけられている.図8.しかし,患者にとっ
ては撮影が行われる場所が,X線撮影室の中であろうが,外であろうが,被曝線
量にはさほど変わりがないと思われる.X線撮影室の設置は,歯科医をはじめと
する,医療従事者に対する,防護策である事を考える必要がある.
放射線防護の基準と3原則
ICRP(国際放射線防護委員会)が,1990年に勧告した,職業被曝に対
する線量限度 を,図9.にあげるが,X線撮影室が設置されていれば問題はな
い.しかし,現行のの医療法にかんがみ,放射線防護の3原則についても,述べ
ておきたい.
放射線防護の3原則とは,・照射時間の短縮.これは,できるだけ,感度の良
いフィルムを使うことにより達成できる.最近,歯科雑誌等でよく目にする,デ
ジタルX線写真装置等は,このメリットが大いにある.しかし,最も簡単で効果
があるのはデンタルX線写真の質を上げる事と,撮影の失敗をなくすことであ
る.・距離を取る.X線の量は,光と同じで,線源からの距離の2乗に反比例す
る.したがって,線源からの距離は,遠ければ遠い程良く,また,X線装置の構
造より,X線が照射される方向(コーンの向きの反対側)の方がエックス線量は
少ない.・遮蔽物を設ける.放射線を遮るもので最もよく知られているものは,
鉛であろう.当院の,X線撮影室の天井と壁には,1・pbの鉛ベニヤが使われて
いる.X線防護衝立なども市販されている.
患者への説明
患者に信頼される歯科医師でありたいと,誰しも思うであろう.しかし,最終
補綴が入るその瞬間まで,患者の審判は確定しない事もある.ならば,患者を自
分のひいき筋にすることも考えたい.そのためには,歯内療法や歯周治療,メタ
ルコアーやマージンの適合など,途中の地道な努力を評価してもらいたい.X線
写真は患者に目に見えない歯周組織の内部を示す資料であるが,同時に,歯科医
師やスタッフが行った,歯科医療行為と患者が行った努力を映す鏡であるかもし
れない.筆者の行える歯科医療には,限界がある.インフォームドコンセントな
どと,かっこいい言葉ではないけれど,治療の経過を患者とともに,泣き笑いし
ながら追ってゆきたいと考えている.
おわりに
これまで6回にわたり,歯科デンタルX線写真について,私見を述べてきた.
最初は自分の持っているX線写真の知識が,表現できればいいと,連載をお引き
受けしたが,初回の原稿を書く途中から,自分のおごりに気付いた.自分の知識
など,総て先輩の先生方より教えていただいたもので,自分のオリジナルなどほ
んの少しであったからである.しかもX線写真は,自分の臨床の未熟さを,露呈
する.しかし,自分が様々に悩み,試行錯誤した事を書き,若い世代の先生方の
なにかの参考になればと,思い直して原稿を書き続け,結果的に,学術的な面よ
りも,体験談を語ることが多くなった.これを読まれた先生方の,回り道が一つ
でも減れば幸いである.
連載を終えるに当たり,歯科医師としての道を導いてくださった,上野道生,純
子先生御夫妻,いつもご指導くださる,北九州歯学研究会の先生方,若若手会の
仲間,途中何度となく励ましていただいた医歯薬出版社の米原さん,そしてなに
より,私にX線写真の手ほどきをしてくださった,故山内厚先生に,感謝の気持
ちを表し,この稿を捧げたい.
これまで,5回にわたり,デンタルX線写真の撮影,現像,読影について述べ
てきた.
しかし,これらはあくまで,歯科医療の一資料の作成方法と,活用(診断)であ
り,資料としての価値を高めるためには,その管理方法が重要となる.言い換え
ると,これまで述べた撮影法,現像法に管理が加わってはじめて,X線写真のハ
ードウェアが,完成すると考えている.
また,我々術者としては,X線写真撮影の有効性を知るが故に,何のためらいも
なく(?),放射線を患者に照射しているが,患者はどう思っているか考えるこ
とも必要である.患者さんよりX線撮影の理解を得るためには,歯科医側より適
切な説明がなされなければならないが,そのために必要な知識を再度整理した
い.これは,医療従事者側の放射線防御にも役立つと考える.
最終回は,この2点について,筆者の考えを述べてみたい.
X線写真の整理・保存
初診時に,X線診断と患者への説明に使用する以外に,筆者がX線フィルムを
見ながら,歯科治療を行う場面は,髄室開放,根管形成,根管充填,メタルコア
ー装着,除石,ルートプレーニング,窩洞形成,歯冠形成,経過観察等である.
このように,X線写真は,撮影した日以外に読影する事も,かなりある.したが
って,X線写真の管理は,筆者にとっては重要な項目である.幸いなことに,筆
者が勤務した上野歯科医院(北九州歯学研究会,上野道生先生)では,すでにこ
のシステムは構築されており,自院開設の折も,そのまま同じシステムを導入し
た.従って,これから述べる事もほとんど,上野先生に教えていただいた事であ
り,現在も感謝の念にたえない.
X線フィルムの中には,画像として口腔内の様々な情報が入っているが,撮影
のデータは,簡単に入れることができない.鋭利な器具でひっかいたり,器械を
使って,文字をフィルム面に入れたりする方法もあるが,筆者はあまり好きでは
ない.また,全顎14枚法と,それ以外の場合は若干,整理,管理の方法が異な
る.
十分な定着・水洗により,長期保存に耐え得るように処理したX線写真を,後
日読影する必要がある時,短時間に抽出できるようにするために,当院では以下
のシステムをとっている.
・フィルムにはあらかじめ,鉛ナンバーシール(NND,⑭ニックス)を貼ってお
く.図1.
・X線写真撮影時に,ワンタッチ式フィルムマウント(FMO,⑭阪神技術研究
所)に,フィルム番号,日付,撮影部位,撮影目的,撮影者を,記入し,あらか
じめ決められた箱に入れておく.なお,この時,14枚法を取った場合は,その旨
を,フィルムマウントに書いておくと.図2.
・現像,定着,水洗まで終えたフィルムは,一晩乾燥させておく.
・翌朝,診療開始時に,番号をあわせて,フィルムマウントにフィルムを貼る.
14枚法の分は,14枚法用のシート(阪神技研)に入れてゆく.枚数が少ないとき
は,モンレックス(東京歯科産業⑭)を使う.図3.
・組み合わせたX線写真は,バインダー(コクヨ・Gファイル)に綴じた専用の
ビニールシート(ASD,⑭阪神技術研究所)に,番号順(日付順)に整理する.
14枚法のフィルムマウントもそのまま,整理する.図4.
・バインダーの最新版は,X線写真整理をする場所(診療室内)に,それ以前の
バインダーは,診療室内の書架に配置する.図5.
・14枚法用のシートは,検査表,指導記録,その他とともに,カルテファイルに
入れる.図6.
システムの長所・短所
先に述べたとおり,当院では一人の患者のカルテは,その他の資料とともにフ
ァイリングする様にしている.したがって,ある一人の患者の当院でのX線写真
撮影の(治療の)履歴は,その場ですぐわかるようになっている.このことを前
提として,このシステムの長所を述べる.
まず,最大の長所としては,過去のX線写真を探す時間が短い事があげられ
る.14枚法は常に,カルテファイルに挟んであるし,フィルムマウントに貼って
ある分も,過去のカルテにより,撮影の年月日さえわかれば,だいたい20秒程
で,出してくることができる.この,短時間で自分の臨床の予後を振り返ること
ができるのは,非常に良いことであると思う.自分の治療の結果が良いのを確認
できるのは,うれしいものである.
次に,14枚法のシートは,プラスチックフィルムのカバー,フィルムマウント
は,ビニールシートに入っているので,裸フィルムの場合と比べて,キズやほこ
りが付きにくいことがあげられる.筆者のX線フィルムのキズは,ほとんどが,
乾燥前に付いたものか,発表用に,スライドシートに入れてからのものである.
このシステムの短所としては,スライド用のプラスチックマウントに入れ替え
るときに,フィルムマウントに付いているフィルムを固定する接着剤が,フィル
ム面に残る事があげられる.貼ってから時間が短い場合はさほどではないが,古
くなると,接着剤が劣化して,扱いにくくなる.周囲0.5・程であるが,スライ
ドにして見るときには,見苦しい.現在,改善策を模索中である.
患者さんにX線撮影を理解していただくために
読者の皆様の中で,患者にX線撮影の事前説明をした際に,自分が妊婦である
ことを告げられ,X線撮影の胎児への影響を問われた経験のある方は,多いので
はなかろうか.
また,妊婦以外でも,全額14枚法のように,多くの枚数の撮影の際に,その理由
を問われることもあるのではなかろうか.
筆者は,チェルノブイニ原発事故,つくば市のウラン工場事故など,放射線障
害に関する,世間の関心事が続く中,術者と患者相互理解の上で,しっかりとし
た知識に基づいたX線写真撮影を行いたいものであると考えている.そのため
に,教科書的な,すこし堅苦しい,事項を述べるがご勘弁いただきたい.
放射線防護の為の基礎知識
我々が,X線診断に利用する放射線の性質としては,1.物質を透過する性質
(透過作用)2.写真フィルムを感光させる性質(感光作用)3.ある物質にあ
たると蛍光を発生させる性質(蛍光作用)4.物質を透過するさい、その物質を
作っている原子や分子にエネルギーを与えて、原子や分子から電子を分離させる
性質 (電離作用)等がある.
これらのうち,透過作用、感光作用、蛍光作用を利用してエックス線検査が行わ
れ,電離作用により,放射線による身体への障害が起きる.
放射線障害の種類としては,身体的影響(早期障害,晩発障害),胚および胎
児に及ぼす影響,遺伝的影響等が挙げられる.ここでは,患者から問われること
の多い,発癌性の問題と,妊娠への影響について述べたい.
患者は,デンタルX線写真のフィルムの大きさから,経験的に歯科での放射線
被曝量は非常に少ないことを知っている.しかし中には,14枚法の時のように,
照射の回数が多くなると不安に思うのも理解できる.このようなときには,ある
一面,申し訳ない気もするが,筆者は医科の胸部X線撮影を,引き合いに出して
説明を行っている.インターネットで,放射線について検索すると,医科では患
者のX線検査に対する不安を取り除くための,対外的な活動が盛んに行われてい
る.様々な情報が公開されており,これを歯科のX線写真撮影が安心である根拠
として利用させてもらっている.以下はその概要である.
デンタルX線写真の発癌性について
人間の体は放射線を多量に受けると、白血病やガンになる可能性があることは
過去の調査よりわかっている.しかし、その放射線の量は、1,000ミリシーベル
ト以上である.この放射線量以下では人体にガンが発生したという確証はない.
一方,集団検診などで使用されるエックス線検査の放射線量は、胸部エックス線
写真1枚で約0.1ミリシーベルトなので、約1万回検査を受けないと1,000ミリシ
ーベルトの量にはならない.歯科のX線写真撮影に使う放射線の量は,もっと小
さいうえ,鉛の入った防護衣も使用しているので,心配しなくても良い放射線量
である.
デンタルX線写真の妊娠への影響
妊娠の場合は,受精後1~2ケ月以内の,本人に自覚のない時期の事より説明し
ているが,なにぶん微妙な問題でもあるので,状況により,説明の仕方を考慮し
ている.
放射線が胎児に与える影響は、受精後から8日までの着床前期であれば、流産
を起こす可能性があるが,この場合本人が妊娠に気付かない事もある.そうでな
い胎児は正常に発育する.受精後2~8週の器官形成期が奇形発生の可能性の最も
高い時期である.しかし,このような影響を与える最低の放射線量は、50~100
ミリシーベルトを越える線量といわれており,歯科でのX線撮影では,全く問題
ではない.
なぜなら,X線を直接照射する胸部エックス線写真1枚で,約0.1ミリシーベルト
なので、胎児に対しての影響は,胸のエックス線写真であると約1,000回を一度
に受けないと100ミリシーベルトの量にはならない.歯科で検査に使用される放
射線量は非常に少なく、さらに鉛の入った防護衣も使用しているので,このよう
に歯科でのX線検査による影響で奇形等の発生する可能性はほとんどない.
放射線防護の対象者
まず最初に述べたいのは,誰のための被曝防護かということである.
患者のX線写真撮影を行うとき,患者にとっては様々なメリットがある反面,X
線に曝露するという,デメリットもある.当然それに対する影響を最小限にする
ために,防護衣の装着は必要である.図7.他方,現在新規に歯科医院を開設す
る際には,X線撮影室の設置が義務づけられている.図8.しかし,患者にとっ
ては撮影が行われる場所が,X線撮影室の中であろうが,外であろうが,被曝線
量にはさほど変わりがないと思われる.X線撮影室の設置は,歯科医をはじめと
する,医療従事者に対する,防護策である事を考える必要がある.
放射線防護の基準と3原則
ICRP(国際放射線防護委員会)が,1990年に勧告した,職業被曝に対
する線量限度 を,図9.にあげるが,X線撮影室が設置されていれば問題はな
い.しかし,現行のの医療法にかんがみ,放射線防護の3原則についても,述べ
ておきたい.
放射線防護の3原則とは,・照射時間の短縮.これは,できるだけ,感度の良
いフィルムを使うことにより達成できる.最近,歯科雑誌等でよく目にする,デ
ジタルX線写真装置等は,このメリットが大いにある.しかし,最も簡単で効果
があるのはデンタルX線写真の質を上げる事と,撮影の失敗をなくすことであ
る.・距離を取る.X線の量は,光と同じで,線源からの距離の2乗に反比例す
る.したがって,線源からの距離は,遠ければ遠い程良く,また,X線装置の構
造より,X線が照射される方向(コーンの向きの反対側)の方がエックス線量は
少ない.・遮蔽物を設ける.放射線を遮るもので最もよく知られているものは,
鉛であろう.当院の,X線撮影室の天井と壁には,1・pbの鉛ベニヤが使われて
いる.X線防護衝立なども市販されている.
患者への説明
患者に信頼される歯科医師でありたいと,誰しも思うであろう.しかし,最終
補綴が入るその瞬間まで,患者の審判は確定しない事もある.ならば,患者を自
分のひいき筋にすることも考えたい.そのためには,歯内療法や歯周治療,メタ
ルコアーやマージンの適合など,途中の地道な努力を評価してもらいたい.X線
写真は患者に目に見えない歯周組織の内部を示す資料であるが,同時に,歯科医
師やスタッフが行った,歯科医療行為と患者が行った努力を映す鏡であるかもし
れない.筆者の行える歯科医療には,限界がある.インフォームドコンセントな
どと,かっこいい言葉ではないけれど,治療の経過を患者とともに,泣き笑いし
ながら追ってゆきたいと考えている.
おわりに
これまで6回にわたり,歯科デンタルX線写真について,私見を述べてきた.
最初は自分の持っているX線写真の知識が,表現できればいいと,連載をお引き
受けしたが,初回の原稿を書く途中から,自分のおごりに気付いた.自分の知識
など,総て先輩の先生方より教えていただいたもので,自分のオリジナルなどほ
んの少しであったからである.しかもX線写真は,自分の臨床の未熟さを,露呈
する.しかし,自分が様々に悩み,試行錯誤した事を書き,若い世代の先生方の
なにかの参考になればと,思い直して原稿を書き続け,結果的に,学術的な面よ
りも,体験談を語ることが多くなった.これを読まれた先生方の,回り道が一つ
でも減れば幸いである.
連載を終えるに当たり,歯科医師としての道を導いてくださった,上野道生,純
子先生御夫妻,いつもご指導くださる,北九州歯学研究会の先生方,若若手会の
仲間,途中何度となく励ましていただいた医歯薬出版社の米原さん,そしてなに
より,私にX線写真の手ほどきをしてくださった,故山内厚先生に,感謝の気持
ちを表し,この稿を捧げたい.